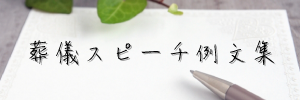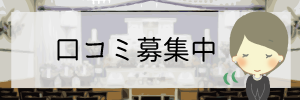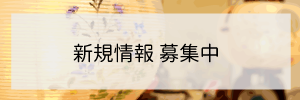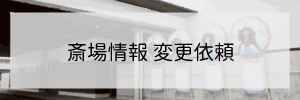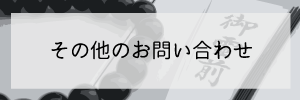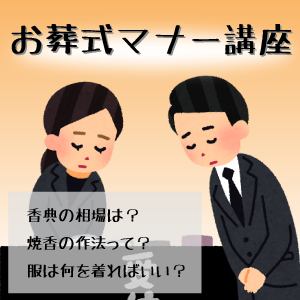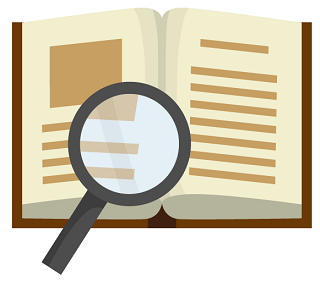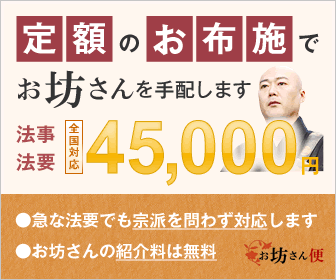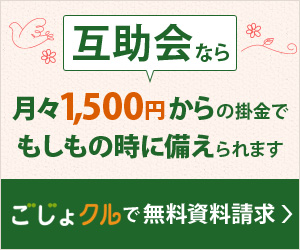葬儀の専門用語 / お水取りとは
お水取りの意味
お水取り(おみずとり)とは、神や仏に対して供える為または自身や家族の為に、寺社仏閣で水を頂くことを言います。
たとえば仏壇の本尊にお供えする水に使用したり、供花用の水として使用したりします。
また、お水取りで汲んできた水を飲むことは御利益があると言われていて、事業や受験や安産などの願いを込めて行われる慣習もあります。
東大寺のお水取り
一方で、一般的な慣習ではありませんが、奈良県奈良市の東大寺の修二会(しゅにえ)という行事の中で行われるお水取りも有名です。
東大寺のお水取りは、仏前にお供えするための神聖な水を若狭井(わかさい)という井戸から汲み上げる儀式です。
「修二会=お水取り」と思っている方もいるほどに、東大寺のお水取りは広く知られています。
なお、修二会は正式には「修二月会(しゅにがつえ)」と言い、全国各地の寺院で毎年3月(旧暦では2月)に行われる行事ですが、やはり東大寺の修二月会が有名です。
お水取りについてのまとめ

お水取りと言いますと東大寺の修二会が広く知られるところですが、神社仏閣で水を頂いてくるお水取りは昔から一般的に行われてきたことです。